
レバノン
ずっと前から行ってみたかったレバノン。ついに訪ねることができた。モスクワ空港のベンチ脇で即席ホームレス状態で一泊。たまたま陣どっだベンチで、ギニアのコナクリから故郷へ帰るレバノン人のグループと一緒だった。とても感じのいい人たちで、大晦日に遊びにいらっしゃいと誘ってくれて電話番号を教えてくれた。その人はとてもいい声をしていて、食堂で食事を待っている間に歌を歌ってくれたりした。
去年、サンアントニオ空港で一泊した時は私たち以外にはほとんど寝てる人はいなかったけれど、ここでは約80人くらいは寝ていたのでなんだか心強い気がした。
しかもありとあらゆる人種の人たち。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中南米…。トランジット・オフィースで食券をもらって食べる食堂での食事も救世軍の炊き出しみたいでなかなかわびしくさせてくれます。日本にいる時は、当然だと思っていたサービスもここでは全く無し!
配膳担当のおばさんたちは、決められたルートの順にまるでロボットのようにもくもくと食事を配るだけ。でも以前は何か話しかけても常に「ニェット」(ロシア語でNO)しか言わなかったのに今回は「シッダン・プリーズ」と「ショー・ミー・ザ・チケット」という新たなフレーズが飛び出したのにはちょっと驚いた。一応ほんの少しずつだけど、おばさんたちもペレストロイカしてたんですね。それに以前はまったく無表情だったけれど、休憩時間にニコニコ楽しそうに談笑していて、その姿を見てなんだかわたしもうれしくなった。
7時間も遅れたけれどようやくレバノンへ出発!レバノンという言葉からくるイメージって、内線、ヒズボラ、アラブ・ゲリラ、廃墟などなんだかキナ臭い物騒な言葉が浮かんでくる。
でもその昔、まだ戦争が起こる前、この国は「中東のスイス」、そして首都ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれていた…。実際に訪れてみて改めてそのことを思い出した。確かに内線中に破壊された建物が旧グリーン・ラインを中心に残ってはいるけれど、街も人々もとても洗練されているという印象を強く受けた。眠りの森の美女が目覚めるように、ベイルートの街も少しずつその美しい姿を取り戻しつつあるように見えた。

旧グリーン・ライン。左の方に見える割れた卵のような建物は元は映画館だったもの。右端の真新しい教会が、この国の人たちの信仰心の厚さを感じさせる。
東ベイルートがキリスト教地区。
西ベイルートがイスラム教地区。
それぞれのモニュメントがあちこちに見られる。内戦中は東西まっふたつに分かれて断絶状態だったので、タクシー運転手でさえ相手地区のことはまだよくわからなかったりする。ベイルート、ジュニエは地中海に面していて冬の季節は雨期。三日に一度くらいの割合で雨が降ったりしていたけれど、この時期は気温は日本の3月頃くらいでとても過ごしやすい。
美しい植物を見ているとここが中東アラブの国だったことを忘れてしまいそうになる。砂漠の中のオアシスゆえに数々の戦争に巻き込まれてしまうことに…。まったく皮肉なこと。

レバノン滞在中ずーと泊まっていたメイス・ホテル。ハムラ地区は日本でいうと銀座みたいなエリア。

毎日同じメニューの朝食。量的にたいしたことないようなのだけど、結構満足感大きい。お客もわたしたちのみの日も多かった。

ウエイターのフセインくん。いつも笑顔でさわやかに応対してくれた。一般にアラブ料理と言われるものはレバノン料理。今までそれぞれ別々にイスラエル、パレスチナ、ヨルダンと訪ねてきて、あれ?名前違ったりしてるけどなんだ同じものじゃないか!ということに、やっと気がついた。でもそれもそのはず。だって、その前は長い間オスマントルコ帝国というひとつの国だったのですから。
ファースト・フードの王様。シュワルマ。羊肉とか鶏肉を香辛料をつけてぐるぐるまわしながらローストしたものをサーベルのような剣でそぎ落として、野菜と一緒にホブスという薄いパンでくるくるっと巻いてくれる。日本でも最近街に車で売っているけれど、本場のシュワルマはチキンや野菜の味が濃くてすごくおいしい。
ファラフェル。揚げたてのひよこ豆で作った丸いコロッケをつぶしてと野菜とタヒニ・ソース(ごまクリーム・ペースト)をつけてホブス(アラブ風ナンみたいなパン)で巻いてくれる。イスラエルのファラフェルはピタ・パン(ホブスより少し小さめで、やや厚い)を半分に切ってポケット状にして、ひよこ豆のコロッケはつぶさず丸いまま中に詰めてくれる。こちらもヘルシーでおいしい。ホンモス。ひよこ豆のペースト。ホブスや野菜につけて食べる。
レバノンのお菓子はとても洗練された味でヨーロッパ風。サイズは日本の約1.5倍〜2倍くらいはある。
どんな店に入っても、日本の漬け物とか韓国のキムチみたいな感じで、たっぷりの生野菜の(ラディッシュ、ミント、にんじん)盛り合わせにオリーブ、ピクルスがつく。私たちは通称お通しセットと呼んでいた。
レバノンではターキッシュ・コーヒーがよく飲まれている。(隣のシリアやヨルダンでは紅茶の方がポピュラー)人通りの多い海岸通りではよくポットでコーヒーを売ってる人がいるし、自動販売機まであった。

屋台の焼き栗屋。こんなちょっとしたところもフランス風です。日本の甘栗というより、むしろ焼き芋みたいな味でした。

LEBANON Cafe 情報
『シティ・カフェ』フランス風オープン・カフェ。
ここのお客さんたちは高級外車(ベンツ、BMWなど)で来ていた。ほとんどのテーブルには携帯電話が置かれていた。普通の電話事情があまりよくないらしい。ベイルートでのわたしたちの御用達の『ウィンピー』。あのハンバーガーのチェーン店だと思うけれど(店内にハンバーガーの写真もあったし…)ハンバーガーを食べている人を一度も見たことなかった。カプチーノにチョコ・クッキーがついてくる。ウエイターの人がみんな感じよかったです。
Web C@fe。インターネット・カフェ。
ここから、日本やレバノン国内にEメールを出した。レバノンの人気歌手マージダ・エル・ルーミーのマネージャーのアブドさんにも「どこからメール送ったの?」と驚かれてしまった。ここは、まだできてから1年くらい。この店のあるエリアには大学や学校が多いので客も学生がほとんど。
ウエイトレスの女の子。なかなかエキゾティックな美人だったので聞いてみたらレバノンとイエメンのハーフだそうです。
システムはアラビア語と英語が入っている。
朝日新聞のホームページもちゃんと見れた。レバノンの有名観光地、『鳩の岩』のすぐ近くのレストラン・カフェ。ベイルートの街の中心部ではアルギーリ(水パイプエジプトではシーシャという)をやっている所は観光地くらい。モンカによるとレバノンのアルギーリの味は甘くて最初はおいしく感じるけれど、だんだん飽きてくるそう。今までで一番おいしかったのは、エジプトのものだったそうです。

アラブ圏の国では、なぜか犬より猫の方をよく見かける。レバノンもどちらかというと猫派。飼い猫なのかノラなのかわからないけれど、あちこちで猫に遭遇した。キリスト教地区のマクハ(アラブ風喫茶店)の老犬。お客さんも老人が多い。
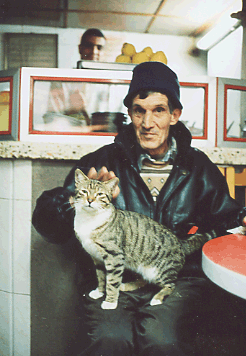
Haret Hrikという街の食堂の猫。店のおじさんにとてもかわいがられていて、夕食にお肉をもらって食べ終わったら口の周りをティッシュで拭いてもらってた。本屋もたくさん行った。戦争の写真集の中にはかなりひどい死体写真なんかもあって、数年前までこんなことがここで行われていたんだと思うと複雑な気分になった。百年前くらいのレバノンの街と人々の写真集を買った。